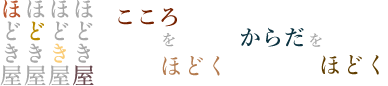私が小学校の頃、家のすぐ近所にひとりのおばあさんが住んでいました。
一人暮らしです。
そのおばあさんは、道に面した古い平屋の薄暗い家の入り口に、古びたタンスをこちら側に向けて
何かを祀っているようでした。
質素なお花とお水をいつも飾っていました。
子ども心に、私はそれは「お仏壇」だろうと思っていました。
田んぼをするでなく、毎日毎日それを祀ることが仕事のようでした。
ときどき道ゆく子どもたちに声をかけては、子どもたちに気味悪がられていました。
なんか変なことをしているふうに見えたからです。
このおばあさんのことを最近思いだしました。
もしかしたら、亡くなったご家族のことを偲んで、お花をあげていたのかもしれません。
特に近所とつきあうこともなく、しかしいつも何かしらそのタンスの上に飾っていました。
私の家にもお仏壇はありましたが、それは家の中で、道路に面して外に見えるようなものではありませんから、このおばあさんはきっと孤独で哀しみのあまりに少しおかしくなっているのでは、という認識が近所の子ども達の間ではありました。
していることは滑稽でしたが、私はそれを笑ってはいけないと思っていました。
たまに飾ってあるしなびたみかんなどをくれようとするのですが、素直に受け取れず、しかし怖がるのも違うような気がして、走って逃げたのがせめて失礼にならないようにとの思いからでした。
当時、変なおばあさんだったその方の「祀る」という行為が、実はとても大事なことで、その方は先祖を大事にすることで十分に役割を果たしていたのではないかと最近になって思えるようになりました。